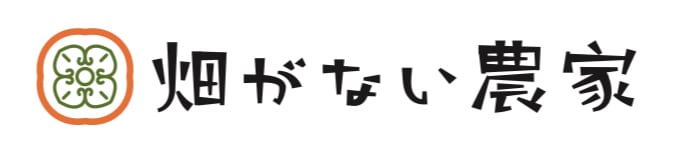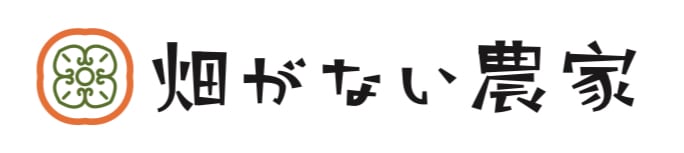-「厄介もの」 を 「宝もの」に-
秋になると、橙色に熟した柿の実を家族で収穫し軒先に吊るす。冬には出来上がった干し柿を囲んでみんなで楽しむ。
そんな当たり前の風景が、故郷の秋田にはありました。
しかし、人口減少・高齢化で収穫する人はいなくなり、地面には落ちて転がる無数の実。
その甘い香りは山から黒い影を呼び込むようになり、
いつからか柿の木は不安の象徴に…。
人の暮らしと野生動物の境界は曖昧になり、
「クマが出るから、あの柿の木は伐るしかない」
そうして一本、また一本と木は姿を消し、
豊かさの象徴だった柿は「厄介もの」と呼ばれるようになってしまいました。
何十年も地域を見守ってきた柿の木が伐り倒され、
風景から消えていくのをただ見ているだけでいいのだろうか?
いや、違う。
問題の根源は「柿の木」ではなく「放置された柿の実」。
伐るべきは木ではなく、
無関心の連鎖「放置」を断ち切ることだ。
だから私はノコギリではなく、高枝切りバサミを手に取った。
みんなで手を取り合い、かつての恵みを取り戻すために。
これこそが、私たちが紡ぐ「あきた柿物語」です。
この物語を読んでくれているアナタも、大切な主人公です。
■ミッション(mission)
放置された柿を「厄介者」から「宝物」へと転換し、 地域の安全・健康・文化を未来へ紡ぐ。
■ビジョン (Vision) ― 三つの未来
①安全な未来
放置柿の減少でクマの出没を防ぎ、子どもや高齢者が安心して暮らせる地域を作る。
②健康な未来
柿の栄養を活かし「天然のサプリメント」として健康寿命を支え、多彩な加工品で食を豊かに彩る。
③持続可能な未来
収穫・加工・販売の利益を次の活動資金とし、柿と共にある文化と風景を未来の世代へ継承する。
■バリュー (Value)
挑戦:現状維持に満足せず、常に新しい解決策や価値の創造に挑む。
共創:世代や地域、企業・行政を超えた協力体制を育む。
循環:資源も知恵も利益も地域に還元し、継続する仕組みを作る。